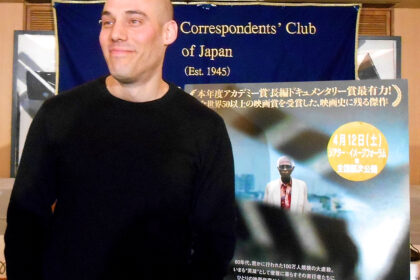ただならぬ「濃密な空気」が漂う「アジアの聖地」の写真。
地下鉄の通路に貼られていたその写真に、思わず目が留まり近づいて見ると、それは、写真家・井津建郎氏の写真展──「アジアの聖地」を告知するポスターだった。しかも、驚いたことにその写真の「聖地」は、私も何度も訪ねたことがある場所、カンボジアのアンコール遺跡群のなかにあるバイヨン寺院だったのだ。
なんていうことだろう。
私自身、何度も自分の目で実際に見たことのある場所だったのに、その写真は、一度も見たことがない表情、気配を醸し出していたのである。ここはどこ? と思うほどに。
写真家・井津建郎氏──。
彼の名前をはじめて知ったのは、カンボジアで長年開催されている『アンコールワット国際ハーフマラソン』を取材している時のことだった。この『アンコールワット国際ハーフマラソン』は、「地雷禁止を訴える」をテーマに、参加費の一部が、地雷犠牲者の自立や義手義足の製造支援などに寄付されるチャリティマラソンである。ところが、大会運営委員の一人、カンボジア人のセム・ファラ氏に話を聞くと、今後このチャリティ活動は、「医療費が無料の小児病院への支援活動にも役立てたい」という。対人地雷被害者をはじめとする障害をもった人びとへの支援のみならず、ひろく恵まれない子どもたちの支援にも取り組んでいきたいということだった。
「田舎の方には子どもがたくさんいますが、医療費が払えず病院に行けない家族が多い。ですから、医療費が無料の病院を応援して、もっと多くの子どもたちが治療を受けられるようにサポートしたいのです」と。
そこで、シェムリアップにある医療費が無料の「アンコール小児病院」のことを調べてみると、その設立者が、ニューヨーク在住の日本人写真家・井津建郎氏だったことを知る。井津氏が「フレンズ・ウィズアウト・ア・ボーダー(国境なき友人)」という NPOを立ち上げて、1999年にシェムリアップに開院した病院で、生後から16歳までの子どもに無料で医療を提供していたのだ。こうして私は、日本人写真家・井津建郎氏の名前を知ることになった。
しかし、どういうわけか、その時は、井津氏がどんな写真を撮影しているかまでは気に留めなかったのである。ニューヨークを拠点に活動している写真家だったので、作品もニューヨークを中心としたものだと思い込んだのかもしれない。理由は定かではないが……。2013年のことである。
そうして10年近くの時が流れた2022年、井津建郎氏が活動50年を迎えたことを記念する写真展──「アジアの聖地」のポスターに、私は偶然にも地下鉄通路で遭遇した。まさに引き寄せられるようにして、その写真と出会ったのである。そして、ふと思い出す。井津建郎氏とは、あのアンコール小児病院を設立した写真家だったはずと。まさか、「アジアの聖地」の写真を撮影していたとは……。
それから数日後、私は、写真展を観にいくことにした。この「アジアの聖地」展は、井津氏がアジア各地の聖地を撮影した写真50点を展示するものだった。展示作品は、「聖地の精緻な質感描写」と、それを包む「濃密な空気」を記録するために、14×20インチ(35×50cm)の大型カメラで撮影して密着プラチナ・プリントに印画されたものだという。しかも、このプラチナ(白銀)を用いた画像は、白から黒までの階調の幅が広く、グレーの調子はほとんど無限に表現することができると解説されていた。これはすごい。どんな微妙なグラデーションの世界がひろがっているのだろうか。
実際、作品を観ると、写真が醸し出す空気感は、想像以上に圧倒的だった。カンボジアのアンコール・ワット、バイヨン寺院、タ・プローム寺院、インドネシアのボロブドゥール寺院、プランバナン寺院、インドのサルナート(鹿野苑)、バラナシ……と、私も訪ねたことがある場所が多く撮影されていたが。井津氏の写真の前に立つと、実際に、そこにいるかのような、濃密で静謐な空気に包まれていったのである。
そう、私も、かつて「アジアの聖地」と呼ばれるこれらの場所で、ふつうとは違う“何か”を感じ、その空気のなかで、さまざまな感情と対話したものだった。その“不思議な経験”の記憶が、井津氏の写真を観ることにより甦ってきたのである。それだけ、井津氏が大型カメラで撮影したプラチナ・プリントによる作品は、聖地ならではのオーラー、“不思議な気配”を映し出していたのだろう。ただならぬ「写真の力」が宿っていた。
そして、井津氏はこう語っている。
大切と思えることは、耳を澄ませて聴くこと。そして自己内面を冷静に見つめること。静かに耳を傾けて気配を聴く時、そこに目では見えなかった“何か”が、見え始めてくることがあるのだという。そう、そうなのだ。耳を澄ませて“気配”を聴くことで、見えてくる“何か”──。それを、その瞬間を、井津氏は見事にとらえていたのだった。祈るように、その時をまち、“気配”を聴きながら、シャッターを切ったのだろう。だから写真を観るものの心、私の心も、揺さぶられる。
こうして、思わぬ巡り合わせで、カンボジアに「医療費が無料の小児病院」を設立した井津建郎氏の写真と出会うことができ、コロナ禍で訪ねることがかなわない、さまざまな「アジアの聖地」の空気を感じることができた。同時に私は、井津氏が、自身のアンコール遺跡の作品収益をもとに、なぜカンボジアに医療費が無料の「アンコール小児病院」をつくるに至ったか、分かるような気持ちになった。
そう、カンボジアには、アンコール王朝が築いた、アンコール遺跡群というすばらしい聖地、その聖なる精神世界がある。しかし一方で、長くつづいた内戦による地雷の被害、戦争の傷跡、貧困で治療費が払えずうしなっていく命……といった人間の業の部分も、今なお多くのこる場所だった。その相矛盾するものが同時に存在する「聖地」にふれた井津氏。
もしかしたら、「聖地」とは、ただただ神聖なる空間をなしている場所ではなく、人間の業の部分までもやさしく包み込み、光を与える場所だと、井津氏は感じたのではないだろうか。それゆえに、「聖地」の「濃密な空気」“光と影”を撮影し、作品として発表するからには、地雷の被害、戦争の傷跡、貧困で治療費が払えずうしなっていく命に対しても、見て見ぬふりはできないと思ったのではないか。そこに光を与えてこそ、「聖地」が「聖地」たらしめるものだから。
つまり……。井津氏にとって、「アジアの聖地」という作品は、「無料の病院を建てて、カンボジアの人々を支援する」という人間の営みを加えることで、はじめて完成するものだったのだろう。井津氏自身は、「カンボジで撮ったもの(作品収益)は、カンボジアへ還すべき」と語っているが……。やはり、そのことにより、自身の心の中に、内なる「聖地」をつくり出すことに至ったように、思えてならなかった。